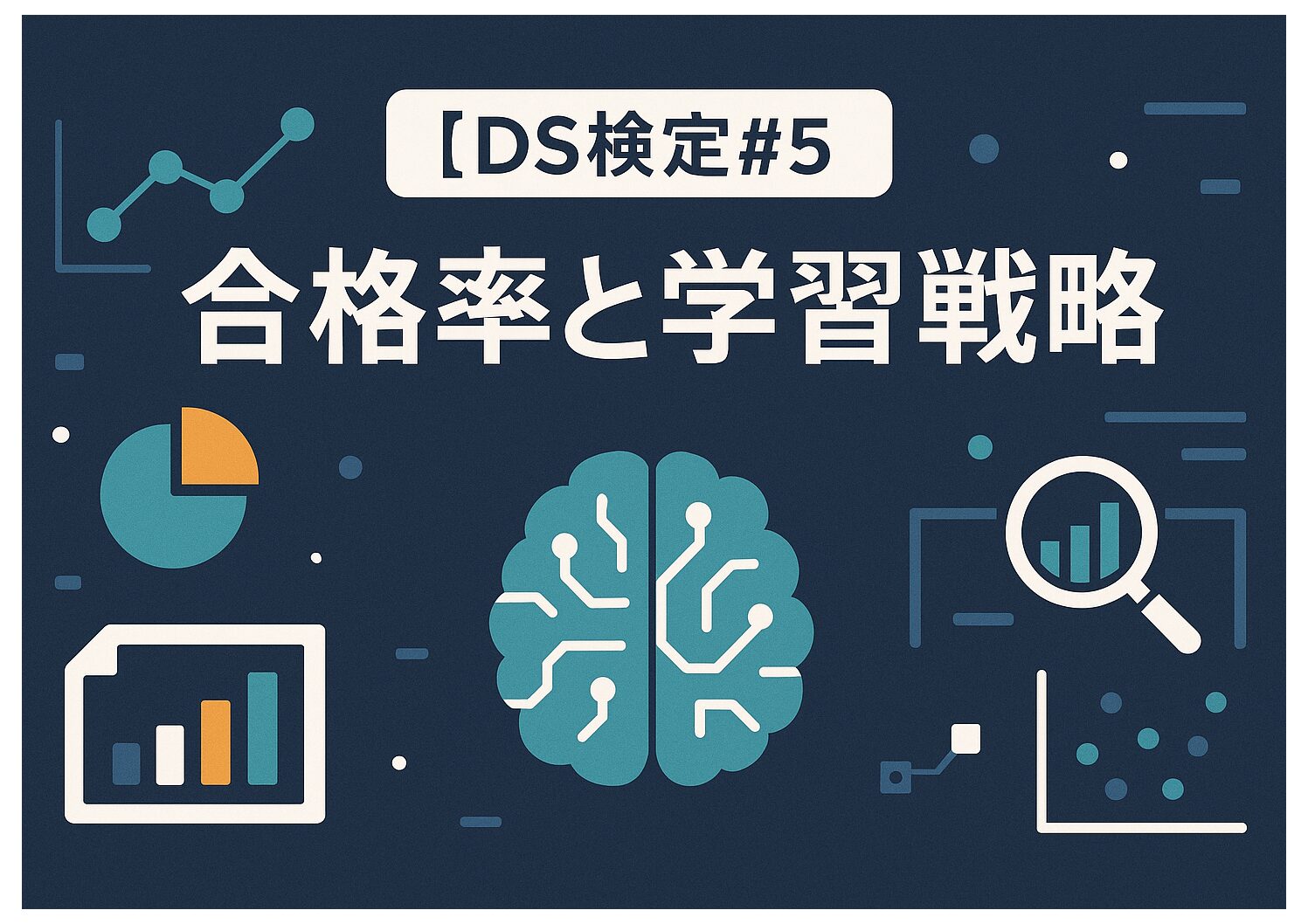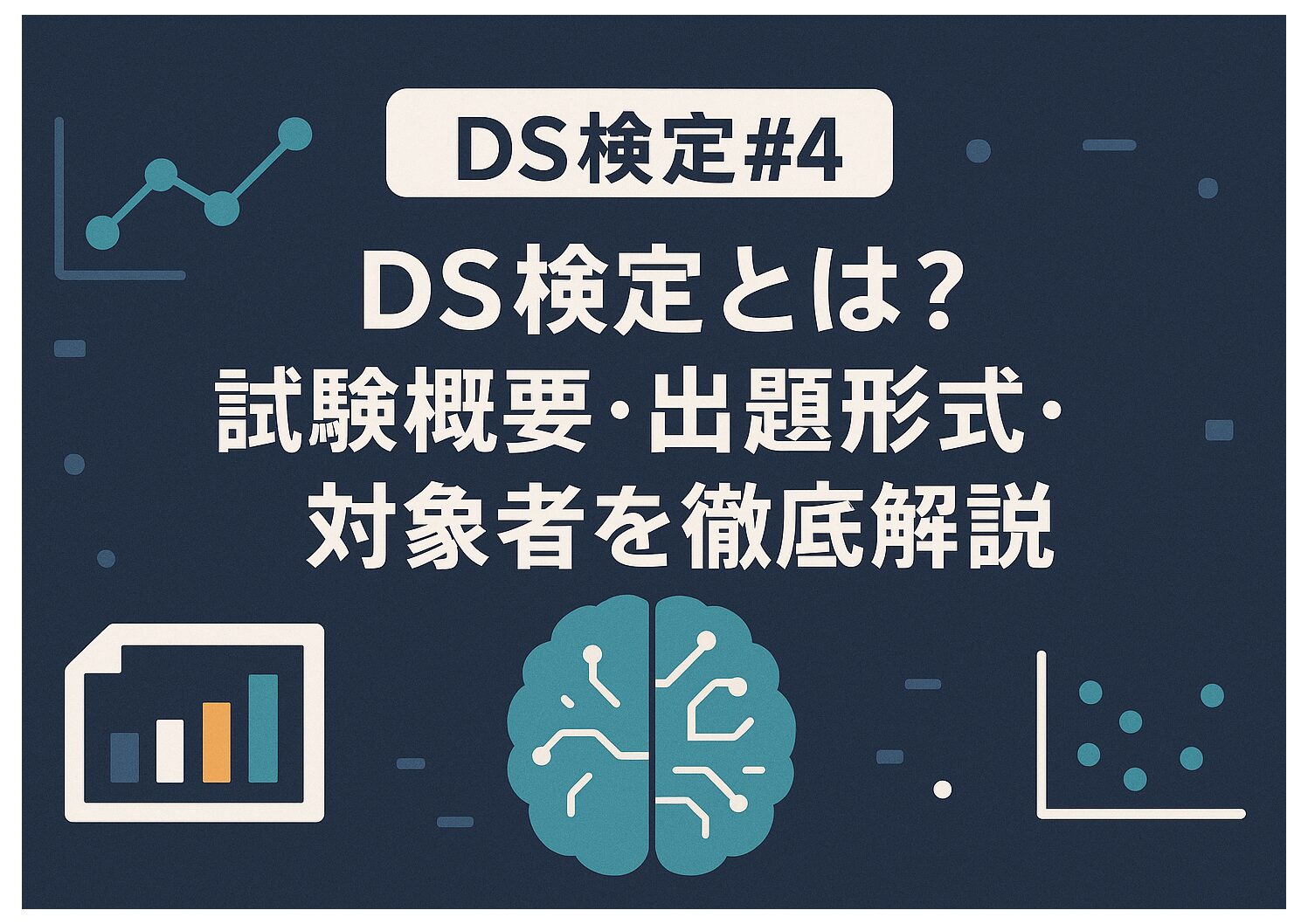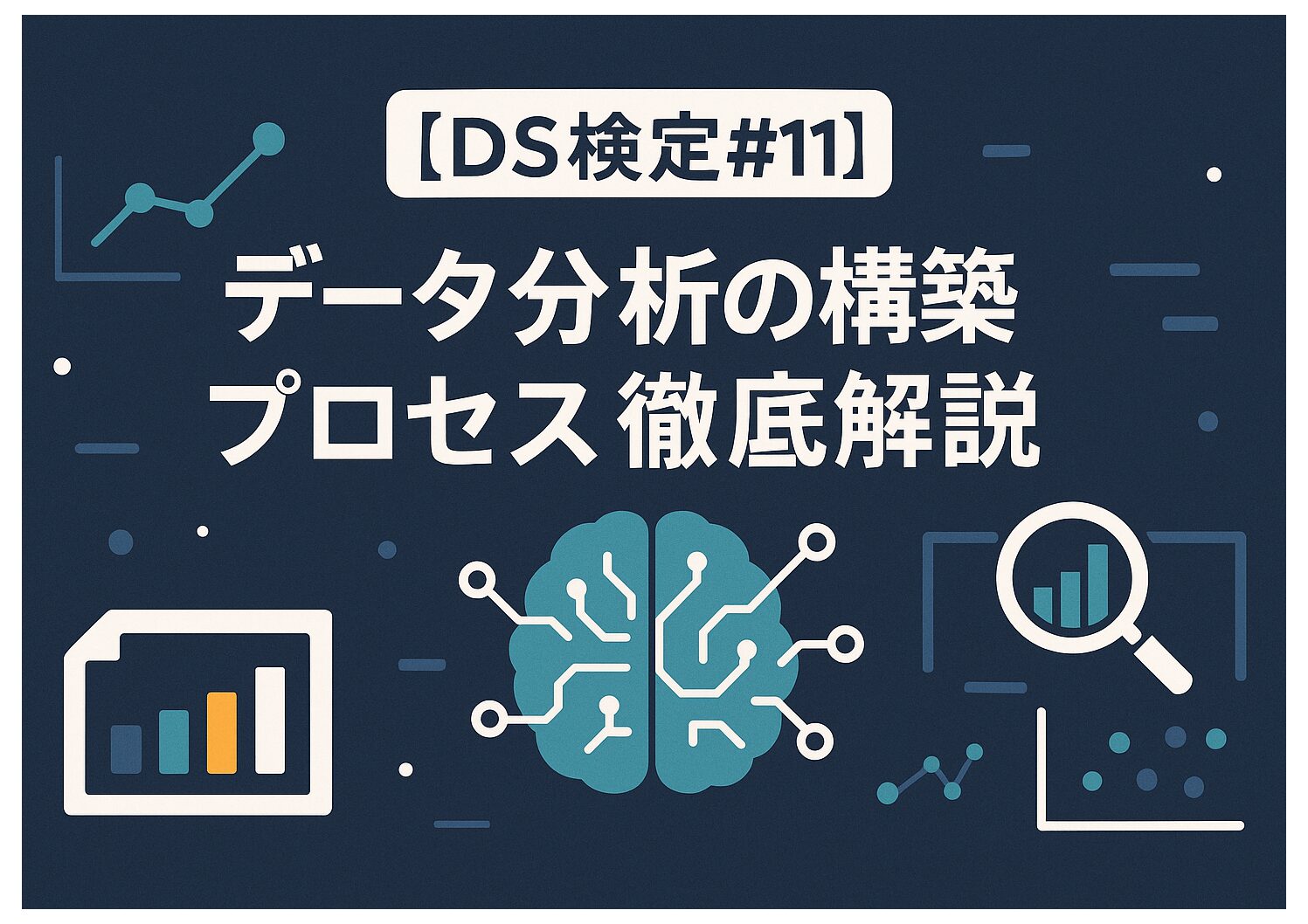この記事はで読むことができます。
「データサイエンティスト検定(DS検定)」に興味があるけれど、合格できるか不安に感じていませんか?
特に、2024年にシラバス(出題要項)が変更され、出題傾向が変化するとなると、多くの受験者が不安を感じるのは当然のことでしょう。
DS検定は、データサイエンス分野での基礎知識と実務能力を証明する注目の資格であり、デジタルリテラシー協議会が定義する「Di-Lite」の一部としても推奨されています。
しかし、単なる用語の暗記だけでは合格が難しい、実践的な応用力や計算力が問われる試験です。
この記事では、DS検定の合格率からその難易度を読み解き、最新シラバスver.5の変更点を詳しく解説します。
そして、これらの変更に効果的に対応し、合格を確実にするための具体的な学習戦略とおすすめの勉強方法をご紹介します。
- データサイエンティスト検定(DS検定)の概要と出題内容
- DS検定取得のメリット
- 最新のシラバス(スキルチェックリストver.5)での変更点と対応方法
データサイエンティスト検定(DS検定)は、一般社団法人データサイエンティスト協会(DS協会)が実施する、データサイエンティスト(アシスタント・レベル)に求められる基礎的な知識と実務能力を証明する資格です。
試験は主に「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」「ビジネス力」の3つのスキル領域から出題されます。
試験形式は**100分で100問の選択式問題(4択)**を解答するCBT形式で、全国の試験会場で実施されます。
DS検定の難易度は、他のデータ系資格と比較すると高めとされています。
例えば、G検定の合格率が60〜70%であるのに対し、DS検定の合格率は約50%で、時には40%台に下がることもあります。合格ラインは**おおよそ80%**とされており、高い正答率が求められます。
これは、単に知識を暗記するだけでなく、知識の応用力や計算力が試される問題が多いことを意味します。
2023年10月に公開された「スキルチェックリストver.5」は、2024年中に実施される第7回試験より適用されました。この改訂は、最新の技術トレンドやビジネス環境の変化に対応するために行われ、全体の出題項目が572項目から650項目に増加しました。
特に注目すべき変更点は、「AI利活用スキル」と「生成AI」に関する新項目の追加です。これらは、データサイエンス、データエンジニアリング、ビジネスの複数の分野にまたがって追加されています。
具体的な追加項目例としては、以下のような内容が挙げられます。
DS検定では、これらのAI・機械学習技術について、アルゴリズムの詳細や専門用語よりも、「データの扱い方とAI技術の応用」という実務的な観点から出題される傾向があります。
DS検定に合格するためには、単なる暗記ではなく、深い理解と実践的なアウトプットの訓練が不可欠です。特に、100分で100問を解くという時間制限の中で、計算力やロジカル思考力を要する問題に迅速に対応する能力が求められます。
以下に、効果的な学習戦略と勉強法をまとめました。
DS検定の勉強を通じて、データサイエンスに関する幅広い知識を体系的に習得し、より実践的な学びや実務への挑戦がしやすくなるでしょう。
合格はキャリアアップの大きな強みとなり、データ活用人材としてのデジタルリテラシーを証明するパスポートとなるはずです。
まとめとして、この記事で解説した内容は以下の3点です。
- DS検定は、データサイエンティストに必要な基礎知識と実務能力を測る資格で、「データサイエンス」「データエンジニアリング」「ビジネス」の3領域から出題される
- 合格すると、データサイエンスの知識を体系的に習得でき、キャリアアップやデジタルリテラシーの証明につながる
- 最新のスキルチェックリストver.5では、AI利活用スキルや生成AIに関する新項目が追加され、その対策も解説
今回はDS検定の合格率と学習戦略、そして新シラバスver.5への対応について解説しました。
次回は、
をテーマに、データサイエンス関連の資格について深掘りしていきます。お楽しみに!